日々の料理には欠かせない食材であるにんじん。栄養があり、鮮やかな色が料理の彩りにもなり、我が家では毎日食卓にあがってます。
ある日いつものように、にんじんを使おうと取り出してみたところ…。

えっ!にんじんの皮が黒い‼︎なんで?!
こんな事ありませんか?このにんじんは食べられるのだろうか?と心配になりますよね。
にんじんの皮が黒い原因がポリフェノールの場合は食べられます。
しかし、軟腐病などの場合は食べられません。カビの場合も食べるのはやめましょう。
にんじんの皮が黒くなる原因は一つだけではないのです。

これってどうやって見分けるの?
見分けることができなければ食べるかどうかの判断ができませんよね。
にんじんの皮が黒い理由や、食べられるかどうかの見分け方、黒くならないようにする保管方法などをご紹介します!
にんじんの皮が黒い原因を見分けよう

にんじんの皮が黒い原因はポリフェノール、軟腐病、カビと出てきましたが、それぞれどのように見分けるのか見ていきましょう。
ポリフェノールが原因の場合

ポリフェノールって、ワインとかに含まれている成分だよね?にんじんにも含まれているの?
ポリフェノールは、ほぼ全ての植物が持つ苦味や渋み、色素の成分なので、もちろんにんじんにも含まれます。
天然の成分なので、ポリフェノールが原因で黒い場合は食べられます。
にんじんにはオキシダーゼという酸化酵素も含まれています。
このポリフェノールとオキシダーゼは別々にありますが、様々な要因で混ざり合います(この混ざり合う要因は後で説明します)
ポリフェノールとオキシダーゼが混ざり合った状態で空気に触れると黒色や茶褐色に変化するのです(褐変と言います)

この褐変はわかりやすい例で言うと、りんごを切ってしばらく置いていると茶色くなる、という現象も褐変なんです。
このポリフェノールによる褐変で皮が黒い場合は、中身は黒くなく普通のにんじんの色をしています。
- にんじんの表面が硬い
- 皮は黒いが切ってみると中は黒くない
- 酸っぱい臭いや腐敗臭がしない
軟腐病が原因の場合
軟腐病は、土壌の細菌が葉、茎、根などの傷口から侵入して繁殖し、にんじん全体に栄養分が行き渡らなくなる病気です。
ヘタ部分から水浸状の淡褐色の病斑ができて次第に拡大していき、進行すると柔らかくなり腐ってきて、悪臭がするようになります。
進行が早いので、買ってきてすぐに黒くなって変わってきたらこれが原因かもしれません。
軟腐病が原因で皮が黒い場合は食べられません。処分しましょう。
- 広範囲で黒くシミのような変色
- にんじんの表面が柔らかい
- 腐敗臭がする
カビが原因の場合
高温多湿など、カビが増殖しやすい環境ににんじんを置いたままにしていると、カビが原因となり黒くなる事があります。
にんじんの皮についているカビそのものを取り除いても中まで侵食している事がありますし、加熱しても死滅しないカビもあるのです。
カビが原因で黒くなっている場合、一部に付いていても食べない方が良いでしょう。
せっかく買ったにんじんでもったいないですが、処分しましょう。
- 黒い部分がへこんだり膨らんだりしている
- にんじんの表面がすす状に黒ずんでいる
- ヌルヌルしていて洗っても取れない
- にんじんの中がドロドロしたりプヨプヨしたりしている
- 強い悪臭がする
以上がにんじんの皮が黒くなる主な原因です。しっかりとみて見分けましょう!
ポリフェノールによる褐変の要因

ポリフェノールによる褐変で黒くなるって言ってたけど、そもそも褐変する要因て何?
すでに説明した通り、ポリフェノールとオキシダーぜが混ざり合って空気に触れると褐変するのですが、その混ざり合う要因はこの3つです。
- にんじん表面の傷
- にんじん表面の乾燥
- 高温下での保存
にんじんは皮が薄い野菜で、これらの要因にさらされやすく、影響を受けやすいと言えます。
<にんじん表面の傷>
にんじんは収穫後にヒゲ根や泥を落とすためにブラシで洗浄されます。この時に皮に細かい傷がついたり、剥がれたりしてしまいます。
これによって細胞膜が壊れてポリフェノールとオキシダーゼが混ざり合い、空気に触れて褐変します。
<にんじん表面の乾燥>
収穫後の洗浄でにんじんの皮に細かい傷がついたり剥がれたりしてしまうと乾燥しやすくなります。
また、にんじんを何かで包んでおかず、そのまま保存していても乾燥していきます。
乾燥でもまた細胞膜が壊れてポリフェノールとオキシダーゼが混ざり合ってしまうので、その結果褐変してしまいます。
<高温下での保存>
にんじんは元々冬野菜ですので、夏のような高温は苦手です。
高温下ではポリフェノールとオキシダーゼが活発になるので、細胞膜が壊れて混ざり合い、褐変してしてしまいます。
流通時は平均10℃で管理されている為黒くなりづらいですが、購入後の保存で高温下に長く置いていると黒くなってしまいます。

それじゃあこうならない保存方法で保存すればいいのね!
では次に、にんじんの最適な保存方法を説明しますね。
にんじんの皮を黒くしない為の保存方法

にんじんの皮を黒くしない為には、適切な温度・湿度の管理と乾燥させない事が大切です。
にんじんの保存には、基本的には冷蔵庫の野菜室での保存が1番望ましいです。
それができない場合は温度変化の少ない冷暗所に置きましょう。

夏は特に冷蔵庫に入れましょう!冷蔵庫で保存する時にもポイントがあります。
冷蔵庫内では立てて保存する
どの野菜にも共通することですが、野菜は育ったように保存すると日持ちが良くなります。
にんじんは下から上に育っていくので、ヘタ部分を上にして立てて保存しましょう。
冷蔵庫内で立てて保存するために、容器などで仕切ると立てやすいです。
私は紙袋を適したサイズに折り込んで使っています。
収納場所に合わせて大きさを変えられるし、汚れたら交換すればいいのでおすすめです。
キッチンペーパーや新聞紙で包んで袋に入れる

冷蔵庫の野菜室は温度・湿度は冷蔵室より高めですが、にんじんは皮が薄いのでただ入れて置くだけでは乾燥しやすく、皮が黒くなりやすいです。
また、スーパーで売られている時は乾燥を防ぐ為に袋に入れられていますが、自宅でもそのまま保存するのはNGです。
水分が溜まり、湿度が高くなるとヒゲ根や芽が出てきて傷みやすくなります。必ず買ってきた時の袋からは出しましょう。
にんじんを冷蔵庫に保存する際にはこのようにして保存しましょう。
- 葉っぱがついている時は切っておく(葉っぱに栄養がいってしまう為)
- 水分を拭き取る
- 一本ずつキッチンペーパーや新聞紙に包む
- ビニール袋に入れる(水分がたまらないよう、口は閉めすぎないようにする)

にんじんをキッチンペーパーなどで包んでビニール袋に入れる事で、乾燥を防ぎ適度な湿度も保てるようにするんだね!
この保存方法で保存すると冷蔵庫内で3週間くらい保存可能です。
少しの手間でにんじんを長持ちさせて美味しく食べる事ができるので、ぜひやってみましょう!
冷蔵庫に入れずに保存する時も同じように保存するといいですよ。
にんじんが萎びた時は
それでもうっかり「にんじんが萎(しな)びてしまった!」という時は、『50℃洗い』がおすすめ!
やり方は簡単!50℃のお湯に数分浸すだけです。これだけで萎びたにんじんがシャキッとします。
これはにんじんだけに限らず野菜全般に使えますのでぜひやってみてください。
『50℃洗い』は、野菜によってお湯に浸す時間が変わります。
スプラウトやハーブなど柔らかい野菜は20〜30秒、葉物野菜は1〜2分、にんじんなどの根菜類は1〜3分、ブロッコリーやアスパラガスなど茎の太い野菜は2〜3分が目安になります。
野菜のサイズなどによっても変わるので、様子を見ながら調整してください。
にんじんの皮はむかないでもいい?

にんじんの皮が黒い場合の見分け方や保存について説明してきましたが、そもそもにんじんの皮はむかないでもいいのか、考えたことはありますか?

え?普通に剥いて食べるものだと思ってた!
説明してきた通りにんじんの皮は薄いので、収穫後の洗浄の段階で剥がれている事も多いです。
そのため、黒くなったにんじんの皮は取り除いて食べた方が良いですが、本来むかないでもいいのです。
緑黄色野菜のにんじんには栄養がたっぷり入っています!
特ににんじんには多くのβ-カロテンが含まれていますが、皮の周辺に多く含まれているんです!
・体内に入るとビタミンAに変化し、作用する
・体の中を錆びつかせない抗酸化作用が高い!
・アンチエイジング、免疫力の強化、皮膚や粘膜を丈夫にする、ガン予防、視力の維持、など
・油と一緒に摂ると吸収力アップ!
また、カリウムも多く含まれており、これは体内の浸透圧を調整してくれるミネラルで、塩分の排出などをしてくれます。
それらのにんじんの栄養を余すところなく摂りたいのならば、皮はむかないで食べればいいのです。
農薬は心配ない?

でも皮をむかないのって農薬が心配…。
野菜を作る上で農薬は、害虫を駆除したり病気を防いだりと必要なものです。
しかし、もちろん体に入る物ですから健康に被害が出ないように国の安全基準を満たした物を安全な使用量で使われています。
収穫時にも洗浄されていますし、市場に出回っているにんじんに農薬の心配はないと思います。
どうしても気になる時は調理する際に表面を流水でしっかり洗えば大丈夫でしょう。
にんじんの皮をむかないメリット
にんじんの皮をむかないことは、栄養を摂れることの他にもメリットがあります。
<時短調理になる>
皮をむかないという事は一つ調理過程が減る事になるので時短につながります。
忙しい主婦にとって、時短になるのは嬉しいですよね!
<ゴミを減らせる>
皮をむかないで食べることで、ゴミを減らせます。特に生ゴミは水分が多いのでゴミを焼却する時の燃焼効率も悪くなってしまいます。
毎日出るゴミを少しでも減らすことで環境に配慮する事になるんですよ!
料理によって変えるのもアリ
皮をむかないと食感や見た目が気になるという場合は、料理によってむく、むかないを変えるのもアリです。
カレーやシチューなどなら皮付きでも気にならないです。筑前煮など色を鮮やかに見せたいときはむいた方が良い場合もあります。
また、スプーンやアルミホイルでこそぎ取るようにむけば、程よく汚れも取れ、あまりむけすぎません。
ピーラーでむいた皮を千切りにしてきんぴらにしたり、かき揚げにしたりしても美味しく食べられますよ!

今まで捨てていたにんじんの皮でもう一品できるなんて、家計的にも大助かりね!
まとめ

- にんじんの皮が黒い原因がポリフェノーの場合は食べられる
- 表面が硬く、中が普通にオレンジ色で異臭がない場合、ポリフェノールが原因と考えられる
- ポリフェノールはオキシターゼと混ざり合った状態で空気に触れると黒や茶色に変化する(褐変)
- にんじんの皮が黒い原因が軟腐病やカビの場合は、食べられない
- 軟腐病は広範囲でシミのような変色があり、柔らかくなり、腐敗臭がする
- カビは表面だけでなく内部まで侵食している場合があり、加熱しても死滅しないものもある
- カビが原因だと黒い部分のへこみや膨らみ、すす状の黒色変化、洗っても取れないヌルつき、内部がドロドロやプヨプヨしている、強い悪臭などがある
- ポリフェノールによる褐変の要因はにんじん表面の傷、乾燥、高温下での保存
- にんじんの保存は、水分を拭き取った後キッチンペーパーや新聞紙に包んでビニール袋に入れ、冷蔵庫内に立てて保存する
- にんじんの皮はむかないで食べるとβ-カロテンやカリウムなどの栄養を摂れるし、時短調理になり、ゴミを減らせて環境配慮になる
- 皮をむかないと食感や見た目が気になる時は、料理によってむく・むかないを変える
- ピーラーでむいたのを千切りにしてきんぴらやかき揚げにしても美味しい
私は小さな頃はにんじんはあまり好きな野菜ではありませんでした。
大人になり、にんじんの美味しさがわかってすすんで食べるようになりました。
自分で調理するようになってからは、栄養価の高さから子どもたちにも食べて欲しくて必ず買って毎日食べさせています。
でも知っているつもりでも意外と知らない事が多くて、調べてみてびっくりしました。
同時ににんじんには知らない良さがあり、ますます食べたい!食べさせたい!と思っています。
皆さんも、にんじんを正しく保存・調理して、栄養いっぱいのにんじんを美味しく食べてくださいね!

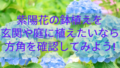
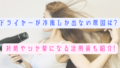
コメント