あなたの家には「ぬか床」がありますか?ぬか床に野菜をつけてぬか漬けにすると野菜が美味しくなるだけでなく、栄養も上がって体にも優しくなります。
私は普段、かき混ぜる手間が少なくていいようにと冷蔵庫でぬか床を保管していたところ、放置しすぎてダメにしそうになったことがありましたが、無事に復活しました。

ぬか床は生き物だから冷蔵庫に入れていてもちゃんと必要な手入れをしないとダメになっちゃうよ!
しかし、完全にダメになってなければ長期間放置してしまったぬか床でもやり方次第で復活させることができます。
今回は、冷蔵庫で長期間放置してしまったぬか床を復活させるにはどうすればいいのかや、ぬかみそを使った郷土料理をお教えします。
ぬか床を冷蔵庫で放置!復活させる方法とは?

冷蔵庫でぬか床を保存するようになればかき混ぜる回数が3~4日に1回で済むので、忙しい人でも自宅で気軽にぬか漬けを作りやすくなります。
しかし、ぬか床を定期的にかき混ぜるのが面倒くさく感じたり、ぬか床を育てるのを挫折して長期間冷蔵庫に放置してしまっていた、という事も少なくありません。
冷蔵庫で長期間放置してダメになったぬか床は、異常な臭いを放つのでふたを開けた瞬間すぐ「使えない」と思ってしまいますが、ちょっと待ってください!
ダメになっているかもしれないぬか床も、次の手順を行うと復活させることができる可能性があります。
ぬか床を復活させる手順と方法
では、ぬか床を復活させる手順と方法をあげてみましたので、一つずつ説明したいと思います。
- ぬか床を冷蔵庫から取り出す
- ぬか床をかき混ぜる
- ぬかを容器に戻し冷蔵庫に入れる
- 翌日ぬか床をもう一度かき混ぜる
- ぬかの味が戻るまで2~4を繰り返す
〈1.ぬか床を冷蔵庫から取り出す〉
冷蔵庫の中でぬか床を長期間放置して使えなくなってしまった場合は、まずぬか床を冷蔵庫から取り出して表面のぬかを1~2センチほど取り除きます。
この時取り除いたぬかは、そのままではとても塩辛くなっているので、数回くず野菜で「捨て漬け」を行い、後でぬかの塩分が薄くなった時に戻します。
ここでいう「捨て漬け」とは捨ててしまう野菜を使ってぬか床に入れることを言いますが、この時に漬かった野菜は食べずに捨てます。つまり「テスト用」なのです。
ちなみに私は、キャベツの外側の、スーパーでも段ボール箱に捨てられているような葉を使っていますよ。
〈2.ぬか床をかき混ぜる〉

ぬか床から出てくる水分は野菜の栄養分だから捨ててはダメ
祖母はよくこう言っていましたので、私は次の工程で「生ぬか」「日本酒」「香辛料」「塩」を入れることにしています。
私は水分を抜くことはせずに「生ぬか」「日本酒(ビールでもOK。ただし蒸留酒はダメです)」「香辛料(輪切り唐辛子、青唐辛子、山椒の実などがおすすめ)」を入れます。
祖母は、「生ぬかは」お米屋さんで米を購入した際に無料でいただいていましたが、最近はスーパーでも販売されています。私もスーパーで購入しています。
しかし「生ぬか」が販売されていない場合もあるかもしれませんよね?そのような時は「いりぬか」でも大丈夫です。
「生ぬか」と「いりぬか」がありますが、使うのはどちらでも大丈夫です。ちなみに祖母は「生ぬか」をふるいにかけたものを入れていました。
「日本酒」を入れる理由は、日本酒に含まれている糖分がぬか床の塩分をまろやかにしてくれるからです。
この時、日本酒を入れる量は少しで大丈夫です。ビールを入れる場合も同様です。ここで注意する事は「一つのぬか床に日本酒とビール、両方は入れない」という事です。

一度日本酒を入れたぬか床にはビールは入れないこと。じゃないと、訳のわからない味になるの!
「香辛料」はいろいろありますが私がおすすめなのは「山椒の実」です。ピリリとした刺激がとても最高です。
山椒の実は、すり鉢で軽くつぶしてから入れると香りが立ってさらに良くなりますよ!ただし、その後目の周りをこすったりすると痛くなるので注意してくださいね。
最後に〈1.〉で取ったぬかをぬか床に戻し、塩を加え、しっかりかき混ぜて冷蔵庫に入れて保管します。
ぬか床が復活するまでは時間がかかります。1日~2日では復活しないことが多いです。ぬか床が復活するまでは、根気よく2~4の4手順を繰り返してください。
福岡地方の郷土料理ぬかみそ炊きの作り方
福岡地方(特に北九州市のあたり)では「ぬかみそ炊き」という郷土料理があります。名前を聞いただけだと「気持ち悪い」と思われるかもしれませんね。
実は私はこの料理を定期的に作る理由があります。それは、ぬか床が増えすぎて困った時によく作るようにしています。
この料理に使う材料は青魚で、「イワシ」や「サバ」で作ることが多いです。普通の煮魚として食べるよりも何だか独特な味と香りで病みつきになりますよ。
お家にぬか床があってぬか漬けを作っていらっしゃるのであれば、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか?この料理は冷蔵庫で1週間ほど保存可能です。
腐ったぬか床とはどんな状態?
腐ったぬか床とはどのような状態のことを言うのでしょうか?一般的にぬか床が使えない状態になってしまったことを指します。
- ぬか床の臭いがおかしい
- ぬか床の見た目や色がおかしい
- ぬか床にカビのようなものが生えている
ぬか床がこのような状態になると使えなくなってしまうので、ある意味では腐ってしまったという事になると思います。
しかし、ぬか床に白いカビのようなものが生えてしまっていた場合、それはカビではなく「産膜酵母」といい、乳酸菌が増えたことによるもので問題はありません。
ただ、産膜酵母が発生した場合は、よくかき混ぜるようにしないと酸味が強くなってしまいます。
このような時は、先述の〈3.ぬかを容器に戻し冷蔵庫に入れる〉の工程をやっていただくと復活できる可能性があります。
ぬか床を冷蔵庫で長期間放置しすぎて使えなくなった時は作り直す
ぬか床は生き物なので、冷蔵庫で保存する場合は3~4日に1回はかき混ぜてあげないといけません。
そのようなぬか床を長期間放置しすぎてしまって復活させようと努力してもうまくいかなかった場合は、思い切って処分し、新たに作り直すのも1つの方法です。
ぬか床というと、「何代にも渡って受け継いでいくもの」と思い込みがちですが、現在は仮にダメにしてしまったとしても何も恥じる必要はないです。
一度ダメにしてしまった経験から新たにぬか床を作り、1から再スタートすることもアリだと思います。
ぬか床を冷蔵庫から常温へ出し入れしてもいい?

結論から言うと、ぬか床は冷蔵庫⇔常温の行ったり来たりは大丈夫です。冷蔵庫から出して常温保管でぬか漬けしたらぬか床がダメになる、という事はありません。
ただ、冷蔵庫から常温へ移動させる時に気をつけてほしい事が2つあります。
- 保存容器のまわりに水滴がつきやすい
- 発酵速度が速くなるので、過発酵にならないように注意
それでは、以上のことをもう少し詳しくお伝えしたいと思います。
保存容器のまわりに水滴がつきやすい
冷蔵庫と常温では温度差がどうしても発生します。そのため、保存容器のまわりには水滴がつきやすくなります。
水滴が容器のまわりにつくと水滴でしみができてしまったり、跡がついてしまうこともあります。
そのため冷蔵庫から出す場合は、ぬか床が外気温に慣れるまでは、置き場所(木製の棚には置かない等)に気をつけたり、ぬか床の入った容器の下に布を敷くなどしてください。
発酵速度が速くなるので過発酵にならないように注意
ぬか床に住んでいる乳酸菌が元気になる温度は20~25℃くらいです。そう考えると冷蔵庫の中はちょっと涼しいので、菌もゆっくり活動しています。
しかし、ぬか床を常温に出してあげると菌にとっては心地よい環境なので、冷蔵庫の中で休んでいた分どんどん活動をし始めます。
そうなると発酵しすぎて乳酸菌が一気に増殖して酸っぱくなってしまうのです。
でも、この2つの理屈を知っておけば十分対策できますので、冷蔵庫に一時保管したり常温で管理したりしても大丈夫ですよ。
ぬか床の冷蔵庫からの出し入れを失敗しないためには
冷蔵庫から常温に出してもおいしいぬか漬けを作り続けるためのポイントは、冷蔵庫と常温の違いをしっかり把握することです。
なぜなら、冷蔵庫で保存していると乳酸菌の活動がゆるやかで、漬かるのも2~3日はかかるし、混ぜるのも毎日じゃなくてもよかったりします。
私はかなりズボラなので、ぬか床をかき混ぜたりかき混ぜなかったりという事がありますが、様子を見てぬかや香辛料、塩を足したりします。
しっかり漬け込んだ味が好きなら、2日くらいおいても全然問題ないですよ。
ただし、常温保存のぬか床は先述にもあるように、乳酸菌が活発になりすぎるので冬場は1日1回、夏場は1日2~3回ほどかき混ぜないと美味しくなくなってしまいます。
ですので、絶対守りたいポイントは「毎日かき混ぜること」です。これが常温保存の必須条件です。
ぬか床が冷蔵庫用として無印良品からも出ています

昔ながらの「日本の食卓」に欠かせないお漬物として「ぬか漬け」は、現在、発酵食品ブームや健康志向の高まりで幅広い世代から注目されています。
ぬか床を1から作るとなるととても大変ですが、「無印良品」の『発酵ぬか床』ですと手軽にぬか漬けに挑戦できると話題になっています。
ここでは「無印良品」の『発酵ぬか床』を使ってみた感想をお伝えします。
自立する袋にぬか床が入って超便利!発酵ぬか床
まずこの「発酵ぬか床」は、すでに発酵済みなのでぬかを育てる手間がない、というのがうれしいポイント!
そして、チャック付きの袋をそのまま容器として使えるので、新しく容器を用意する必要もなく、袋が自立しているので野菜の出し入れも簡単です。
- お好きな野菜を準備し、洗う
- 大きさによって、適当な大きさにカットする
- 水気をしっかりふき取って、発酵ぬか床の中に埋め込むように入れていく
- 袋の裏面に野菜ごとに漬ける時間の目安(12時間~)が書かれているので、参考にしつつ好みの時間で冷蔵庫に保管する
- ぬかを水で洗い流して、食べやすい大きさにカットして完成です!
今回は午前11時頃から翌朝の8時まで、およそ20時間ほど漬けて取り出してみました。
水洗いした後で切ったばかりの時は、少し塩味が強いかな?と感じましたが、その日の夕飯でいただくと、味がなじんで美味しいぬか漬けになっていました。
発酵ぬか床は何度も使えるのでコスパもいい!
なんとこの『発酵ぬか床』は使い捨てではありません。少しのお手入れで何度も使うことができ、お手入れの方法も裏面に書かれているので安心です。
ぬかが減ってきた時には、便利な「補充用250g」も販売されているし、本当に「え?本当にこれだけ?」と言ってしまうほど、簡単で本格的なぬか漬けを味わえます。
しかも、使っていくうちに“自分だけのぬか床”が完成していく楽しみがありますよね?
失敗しない“ぬか床デビュー”をしたいなら「無印良品」の『発酵ぬか床』はおすすめです。是非、この機会に試行されてみてはいかがでしょうか?
まとめ

- ぬか床は生き物であり、放置しても完全にダメになっていなければ復活させることができる
- ぬか床を復活させる手順と方法がある
- ぬか床を冷蔵庫から取り出して、表面のぬかを1~2センチほど取り除く
- ぬか床をかき混ぜた時に上がってきた水分は捨てない
- ぬかを容器に戻し冷蔵庫に入れる際には「生ぬか」と「香辛料」「塩」「日本酒」を入れる
- 香辛料でおすすめは「山椒の実」
- 翌日もう一度ぬかをかき混ぜて、くず野菜を入れて捨て漬けをする
- ぬかの味が戻るまで根気強く繰り返す
- 福岡地方には「ぬかみそ炊き」という郷土料理がある
- ぬか床に白いカビのようなものが生えていても、それはカビではなく「産膜酵母」である場合が多い
- ぬか床を冷蔵庫で長期間放置しすぎて使えなくなったら作り直す
- ぬか床を冷蔵庫から常温への出し入れしても大丈夫
- 常温のぬか床は発酵速度が速くなるので、過発酵にならないように注意する
- 無印良品からも何度も使えるぬか床が販売されている
以上がぬか床を育てる場合、冷蔵庫だと一定期間放置しても大丈夫という記事でした。
私は実家にいた頃はぬか床を触ったこともなかったのですが、祖母のぬか漬けは本当に美味しかったので味を覚えていたからか、割とすぐに美味しく作ることができました。
初めてぬか床を作ってみるなら無印良品の『発酵ぬか床』を利用して、香辛料を増やして自分流の味を作ってみてもいいかと思います。
「香辛料を定期的に足していって香辛料だらけにならないの?」と祖母に聞いた事がありますが、面白い回答が返ってきました。
「ぬか床にいる酵母菌が食べてしまうから定期的に足していっても大丈夫なの」という事でした。
祖母が使っていたぬか床は、なんと祖母のおばあちゃんの代から100年以上続いたものだったので納得がいきました。
これからぬか漬け作りに挑戦するなら、ぬかを足すだけではなくて、香辛料や塩にもこだわりを持ってやってみるとすごく美味しくなると思うので、ぜひ挑戦してみてください。

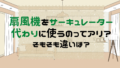
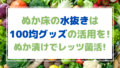
コメント