飼っている猫ちゃんのトイレに欠かせないものと言えば「猫砂」。
そんな猫ちゃんですが、時々トイレをした後に砂かきをせず、トイレのヘリや壁をカリカリとかくことはありませんか?
実は、これ、トイレを気に入っていないという猫ちゃんからのSOSなのです。
買い替えたばかりだと、素材の感触が合わなかったのかと思いますが、今まで使っているものだとなおさら疑問に思うことでしょう。
猫たちがトイレに不満がある行動を示す原因は、猫砂の素材というより、砂の量が関係しています。
そこで、この記事では、猫用トイレの砂の量について徹底解説します。
「キレイ好きで、トイレへのこだわりも強い」と言われる猫ちゃんが快適に過ごせるように…。
是非この機会に砂の量や交換時期を見直しましょう!
猫の理想的なトイレの作り方は猫砂の量で決まる!?

猫は本能的に排泄物を砂の中に隠す性質があるため、ある一定量以上の砂の量をトイレ内に入れておく必要があります。
いきなりですが、猫用トイレの砂の量はどのくらい入れていますか?
猫砂の量は少なくても多くても、猫にとってストレスの原因になってしまいます。
特に、砂かきをしたときに、トイレの底が見えてしまうのは、砂の量が少なすぎですよ。
つまり、理想のトイレの作り方は猫が「砂かき」をできるかどうかです。
猫は、トイレに入って砂をかき、排泄した後、砂をかけて隠してから出ていきます。
排泄後に砂かきができないほど砂の量が少ないと、トイレを避けたり、トイレ以外のところで粗相したりしてしまいます。
また、猫砂が少量だと、トイレの底にうんちやおしっこがついてしまい、掃除が大変になるでしょう。
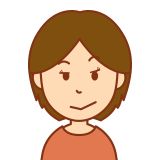
しっかり砂かきをして猫の欲求を満たすことも飼い主のするべきことなのです♪
猫砂の深さは、一般的に3cm〜7cmがちょうどいいと言われています。
飼っている猫によって、好みや使いやすさが違うので、初めは多めに入れて様子を見るといいでしょう。
猫があまりに多く飛び散らかしていたり、使いにくそうにしていたりする場合は、徐々に砂の量を減らしてみてください。
猫の理想のトイレは大きさにもこだわって!
猫にとって理想のトイレを作るときに欠かせないポイントは、砂の量だけではありません。
猫はトイレの大きさにもこだわりが強く、好き嫌いを左右します。
猫は、マーキング行為と違って、おしっこするときはしゃがんでします。
その時に、お尻にフチが当たってしまうのをとても嫌がります。
トイレのヘリに足をかけて排泄している場合は、窮屈というサインですので、見逃さないでください。
つまり、理想のトイレの大きさは、猫の体長の1.5倍以上ということになります。
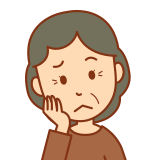
飼っている猫は体長が長いから、市販のトイレでは小さいかも…。
大きめのトイレが欲しいという人は、衣装ケースが一番使い勝手がいいですよ。
- トイレの中で方向転換できるくらい余裕がある
- しゃがんだ時にお尻がフチに当たらない
猫用トイレの砂の交換方法や頻度は?どう捨てる?

猫にとって必需品であるトイレですが、猫砂の交換や掃除を怠ると悪臭がするだけでなく、病気の原因になります。
排泄物を取り除かないでいたり、猫砂の交換を怠ったりしていると、猫のトイレはどうなってしまうのでしょうか?
- 悪臭がする
- 猫砂の本来の効果が期待できない
- 病気の原因になる
- 猫がトイレで排泄しなくなる
消臭効果がある猫砂を使っているから大丈夫と思っていませんか?
消臭効果があっても、猫砂を交換せずに使い続けると、本来の効果を発揮しなくなります。
また、固まるタイプや崩れるタイプ、崩れないタイプの猫砂は、使い続けるうちに悪臭を放つようになります。
つまり、キレイ好きな猫にとって、トイレを清潔に保つことは基本中の基本なのです。
猫は、水皿にひげが付くのを嫌がり、一度嫌な思いをすると絶対に同じ容器では飲んでくれません。
そんなこだわりの強い猫が、トイレが汚いと感じると、トイレ以外の場所で排泄するようになります。
猫に限らず、人間も前の人がトイレを流し忘れていたら、不快に思いますよね。
常に清潔なトイレを保つようにしてあげてください。
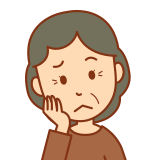
排泄物をそのままにするとなぜ病気の原因になるの?
排泄物が付着した猫砂は悪臭を放つだけではなく、菌を繁殖させます。
その繁殖した菌が猫の体に付着したまま、毛づくろいすれば体内に取り込むことになるでしょう。
猫は暇さえあれば毛づくろいしているので、トイレの菌が原因で病気になるというリスクも否めません。
このように、猫砂の交換や掃除をしないだけで、猫に負担をかけることになるので、こまめに交換するようにしましょう。
猫用トイレの掃除はどのくらいの頻度がいい?
オススメのトイレ掃除方法は、猫砂を交換するタイミングでトイレ全体を丸洗いすることです。
掃除の頻度は、毎日と月1回あり、それぞれのタイミングですることが違うので注意点を確認しましょう。
〈排泄物は毎日掃除する〉
1日数回は、付属のスコップで排泄物が付いた部分の猫砂を取り除くようにしましょう。
ただし、砂かきができるように、減った分の砂を必ず足しておきます。
汚れた範囲が広く、猫砂を取り替える量が多い場合は、古いものを残しつつ、新しいものを足すようにしましょう。
猫は砂に自分の臭いが付いていると、安心できる場所と認識するからです。
〈月1回は猫砂の交換とトイレの丸洗い〉
猫砂は、月に1回は全ての砂を入れ替えるようにし、そのタイミングでトイレも丸洗いしましょう。
平均的な頻度は月1回が望ましいと言われていますが、その前に臭いが気になり始めたらすぐに交換するといいです。
トイレを丸洗いする場合は、お風呂場で60℃以上の熱湯で洗うと、除菌することができます。
しかし、大抵の猫用トイレはプラスチック製になるので、丸洗いする前に耐熱温度が60℃以上であるか確認してください。
使用後の猫砂って何ゴミに分別すればいいの?
猫のトイレで一番質問が多いことといえば猫砂の正しい捨て方とごみの分別。
猫砂の素材は、紙製やシリカゲル、木系、鉱物系、おからがあり、素材によって捨て方が違うので困っていますよね。
素材別の猫砂の捨て方は大きく分けると次の3パターンあります。
- トイレに流す
- 燃えるゴミで出す
- 燃えないゴミで出す
実は、猫砂の素材や住んでいる自治体によって、猫砂の取り扱いや捨て方が違うので、これが正解というものはありません。
しかし、猫の排泄物は臭いがきついので、ご近所トラブルに発展しやすいということを忘れてはいけませんよ。
〈トイレに流す〉
主に、紙製や木製、おからを原料とする猫砂は、トイレに流すことができます。
商品に「トイレに流すタイプ」と書かれたものだけ流すようにしてください。
トイレに流す場合は、排泄物が付着した猫砂だけ流すようにしましょう。
特に、固まるタイプの猫砂には、吸収性ポリマーが含まれているので、大量に流すと詰まります。
〈燃えるゴミで出す〉
主に、紙製や木製、おからを原料としている猫砂は、「燃えるゴミ」として出すことができます。
トイレに流せるタイプであっても、猫砂を全交換した場合は燃えるゴミとして出してもいいかもしれません。
ちなみに、自治体によって、うんちだけトイレに流してと決められていることもあります。
〈燃えないゴミで出す〉
シリカゲルや鉱物系を主原料とする猫砂は、燃えないゴミとして取り扱われることが多いようです。
猫砂を可燃と不燃のどちらで取り扱うかは、自治体によって判断が違うので、捨てる前に確認が必要です。
猫がトイレで寝るようになったら病気の可能性も?

ご飯を少しだけ残したり、ご飯に砂をかけたり、ときどきミステリアスな行動を取る猫。
不可解な行動だと思いますが、一つ一つにはちゃんと意味があるのです。
猫は、トイレに不満があると砂かけをしないことがあるのは既にご説明しましたよね。
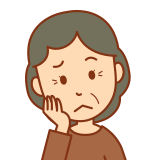
我が家の猫が最近トイレで寝るようになりました…。
トイレが落ち着く、お気に入りであればいいけど、病気の可能性もあるのではないかと行動の意味が気になりますよね。
トイレで寝る子、寝ない子はバラバラですが、何らかの原因が生じていることは確かです。
では、猫がトイレで寝るという行動にはどんな意味があるのでしょうか?
猫によって様々ですが、トイレで寝る原因は次の3つです。
- 自分の臭いがして安心する
- ストレスを感じている
- 病気の可能性
〈自分の臭いがして安心する〉
引越しなどで生活環境がガラリと変わると、猫がトイレで寝るのはよくあることです。
なぜなら、引越し先で自分の匂いが唯一染み付いているものだからです。
環境の変化で猫にも負担をかけているので、慣れるまでは大目に見てあげましょう。
〈ストレスを感じている〉
キレイ好きな猫がトイレで寝るようになるのは、飼い主への当てつけかもしれません。
猫は、トイレを「汚いもの」とちゃんと認識しています。
それでもトイレで寝るということは、飼い主やトイレ以外の所にストレスを感じている可能性があります。
例えば、動物病院へ連れて行った日や、部屋に芳香剤が充満している場合が考えられます。
〈病気の可能性〉
子猫や高齢猫は、トイレをトイレと認識していない場合があります。
子猫の場合は、遊ぶ場所ではないことを教えると覚えますが、高齢猫の場合は、認知症の可能性が考えられます。
高齢になると、排泄のコントロールができなくなり、寝たままおしっこをすることがあります。
そのため、移動せずにトイレで寝たり、起きたりしている猫は少なくありません。
また、猫が膀胱炎や頻尿だと、おしっこが出にくくなり、長時間トイレに座ったまま疲れて寝てしまうことがあります。
頻尿は腎不全が関係していることもあるので、病院に連れて行くことを検討しましょう。
まとめ

- 理想的な猫用トイレの作り方はトイレの大きさと猫砂の量で決まる
- 猫は排泄物を砂の中に隠す性質があるため、ある一定量以上の砂の量をトイレ内に入れておく
- 猫砂の深さは3cm〜7cm程度、トイレの大きさは猫の体長の1.5倍以上
- 猫砂の量が少ないと、底に排泄物が付いてたり、猫自身が砂かきできなかったりするため、ストレスの原因になる
- 猫砂は初め多めに入れて、飛び散るようなら徐々に減らしながら調整する
- トイレの大きさは、しゃがんでもお尻がフチに当たらない、トイレの中で方向転換できるものがいい
- キレイ好きな猫にとって、トイレを清潔に保つことは基本中の基本
- 猫砂は排泄物が付着したまま、掃除を怠ると菌が繁殖し、衛生状態が悪くなる
- 猫は毛づくろいするため、トイレが汚いと菌が原因で病気になる可能性がある
- 排泄物は毎日取り除き、月1回の猫砂を全交換するタイミングでトイレを丸洗いして清潔さを保つ
- 猫砂をトイレに流す場合は、一度に流すとトイレ詰まりの原因になるため少量ずつ流す
- 猫砂を可燃または不燃ゴミで出す場合は、住んでいる地域の指示に従う
- 猫がトイレで寝る原因は、ストレスや病気が関係している
お家時間が長く散歩をしない猫にとって、トイレは生活の一部であり、安心できる場所なんですね。
猫が不可解な行動をしても、焦らず原因を追求することが大切です。
言葉が通じないからこそ、よく観察して小さなサインを見逃さないようにしましょう。
猫が健康に暮らせるよう快適な環境づくりを心がけましょう。
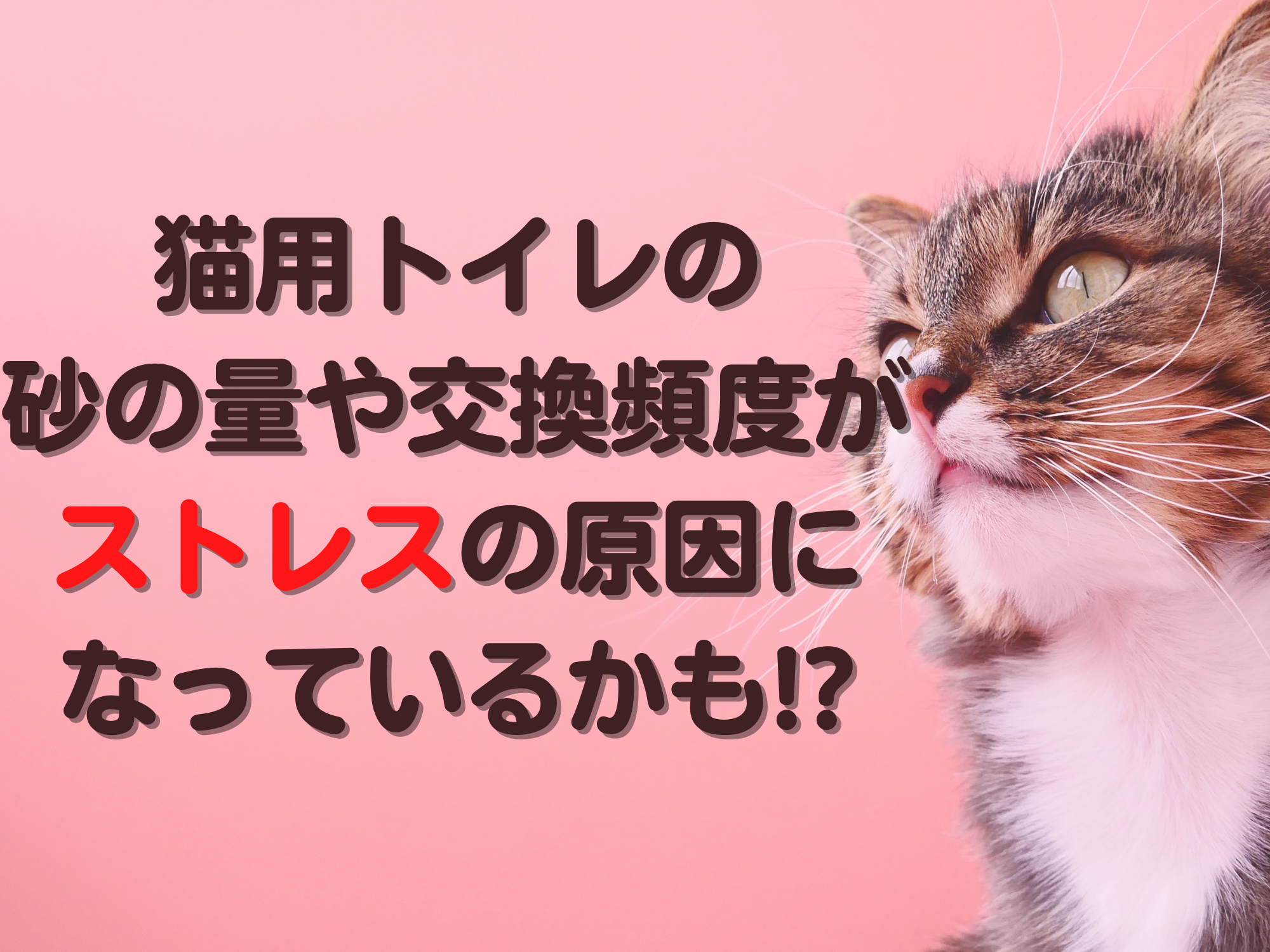

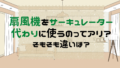
コメント